飲食店を開業する際、物件を借りるだけではなく、保健所による営業許可や消防署への届出など、さまざまな手続きが必要です。
また提供を予定している飲食物の種類や提供方法によって、営業許可の種類が異なります。
その種類によって必要な設備や、調理を行うスペースの要件が定められています。
特に2021年(令和3年)6月からは食品衛生法が改正され、業種の再編などが行われたため、最新情報での確認が必要です。
また営業内容によっては保健所による営業許可だけでなく警察署に届出が必要なものもあります。
では、業種ごとの許可の種類や、注意が必要な営業形態について、どんな準備や届出が必要なのか見ていきましょう。
飲食業許可とは、飲食店を開業するために必要な公的な許可です。
食品衛生法に基づき、飲食店の施設や設備、食品の取り扱い方法などが衛生的であることを確認するために設けられています。
調理したものを提供し、店内で飲食してもらう業態はすべて飲食店に分類され、営業を行うには保健所から飲食業の営業許可を受ける必要があります。
営業許可を受けるには定められた施設基準を満たす物件であることが条件です。
地域によっては多少の違いがある場合もありますが、
・調理場と客席等の部分を区画するためドアーを付けること
・調理場の壁・天井は平滑で清潔で掃除しやすい構造であること
・内壁は床から1m以上耐水性の材質で清掃・洗浄しやすい構造であること
・調理場の床は耐水性材質で排水が良好なこと、平滑で清掃・洗浄しやすい構造であること
・調理場には食品・容器・器具を洗浄するため流水式の2槽以上のシンクを備え付けること
・調理場には食器等の容器・器具を殺菌するため給湯器等の消毒設備を設けること
・調理場には流水式手洗い設備を設け、消毒設備を備え付けること(2槽シンクとは別に必要)
・調理場には食品を保存するため、十分な大きさの有る冷蔵設備を設けること
・調理場には食器等を衛生的に収納できる扉つきの戸棚を備えること
・調理場にはゴミ箱はふた付きで耐水性で十分な容量があり、汚液や汚臭が漏れない材質の容器であること
・調理場には、ばい煙・蒸気等の排除のため換気扇・ダクトなど排除設備があること
・調理場の窓には網戸、排水口には金網などを付けて昆虫やねずみ等が侵入しない設備にすること
・調理場の作業面における適切な照度(100ルクス)を保ち得る照明設備を設けること
・水道水又は飲用の水を供給できること(貯水槽・井戸水は水質検査表の提出が必要)
・トイレには流水式手洗い設備を設け、消毒設備を備え付けること(調理場と離れていること)
・食品衛生責任者プレートの掲示
といった項目があり、これらを満たしていないと営業許可を受けられません。
営業許可を受けるにはまず、厚生労働省の「食品衛生申請等システム」から必要事項の入力を行い、必要なファイルを添付し申請します。
後日、管轄の保健所から検査日程などの連絡が来ますので、日程調整の上で、現地検査を受けます。
また飲食店には、食品衛生責任者を置く必要があります。
食品衛生責任者の資格は、栄養士、調理師などの有資格者か、所定の講習の受講修了者が取得できます。
講習は丸一日かけて行われます。
受講するには事前申込みが必要です。各地で頻繁に行われていますが、先の日程まで予約が埋まってしまっていることが多いので、早めの申込みがおすすめです。
居酒屋、スナック、バーなど、お酒を中心に提供する飲食店を開業したい場合、営業内容や営業時間によって警察署への届出や許可が必要となる場合があります。
立ち飲み屋、ダイニングバーなどの主にお酒を提供することを目的とした業態でも、深夜0時から午前6時までの深夜時簡帯にそもそも同業態にて営業をしないのであれば、深夜酒類提供飲食店営業届は必要なく飲食店営業許可で営業することができます。
お酒を中心に提供する飲食店の場合、通常認められている営業時間は深夜0時までです。
深夜0時を超えて営業する場合、警察署に深夜酒類提供飲食店として届け出る必要があります。
深夜酒類提供飲食店として営業するためには、飲食店営業許可を受けた上で、以下のような店舗の条件を満たす必要があります。
・営業所内(客室内)の照度を20ルクス以下とならないような構造または設備であること。
・客室の床面積は9.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が1室のみの場合は、特に制限はありません。
・客室内に見通しを妨げる設備(おおむね1m以上のもの)がないこと。
・善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
・客室の入口に施錠設備を設けないこと。ただし、営業所以外の直接通ずる客室への出入口については特に制限がありません。
・ショーを見せるなど、深夜において客に遊興させないこと。
・営業所周辺における騒音または振動の数値が、各都道府県の条例で定める数値に満たないように維持されるために必要な構造または設備を有すること。
・営業所周辺において、各都道府県の施行条例で定める数値以上の騒音または振動(人声その他の営業活動にともなう騒音または振動に限る。)が生じないように、その深夜における営業を営まなければならないこと。
スナックやキャバクラなどスタッフがお客さんに接客する営業スタイルの場合、風営法における接待飲食店営業(風俗営業)を行う店舗として、警察署の許可を受ける必要があります。
注意したいのは、風俗営業の場合、営業時間は深夜0時までしか認められていないことです。
また、同一店舗で風俗営業と深夜酒類提供飲食店の両方を行うことは認められていません。
風俗営業に該当する行為を許可を受けずに行うと、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が課される刑事処分や、営業停止命令など行政処分に問われることがあります。
スナック、バーなどを開業する場合、深夜酒類提供飲食店か、風俗営業のどちらで届出、許可申請を行うのかを決め、ルールに則った営業を行いましょう。
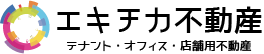
 お気に入り
お気に入り