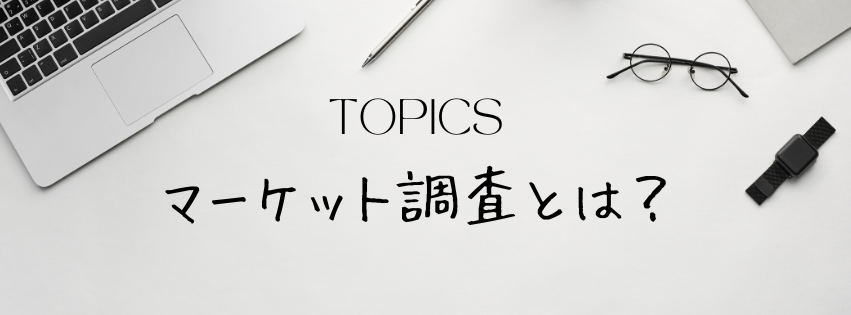 マーケット調査とは、市場に関する情報を収集し、分析することで、市場の現状や動向を把握する活動です。
マーケット調査とは、市場に関する情報を収集し、分析することで、市場の現状や動向を把握する活動です。
マーケット調査によって得られた情報に基づいて、商品やサービスの開発・改良や新規事業の立ち上げ、マーケティング戦略の策定からはじまり、顧客満足度の向上にもつながります。
マーケット調査は、大きく分けて定量調査と定性調査の2種類があります。
定量調査は、アンケート調査や統計データ分析などを行い、数値的なデータを収集する方法です。
市場規模や顧客の属性、購買行動などを把握するのに適しています。
定性調査は、インタビューやグループディスカッションなどを行い、顧客の意見や態度を深く理解する方法です。
顧客のニーズや潜在的な需要を把握するのに適しています。
近年では、ビッグデータやAIなどの技術を活用したマーケット調査も盛んに行われています。
これらの技術を活用することで、より迅速かつ精度の高い調査が可能になっています。
新規事業を考える際に最も大事なのは「ターゲットとするお客様はどういった方か」です。
ターゲット顧客の属性(年齢、性別、職業、収入など)、行動(購買行動、メディア利用状況など)、価値観(ライフスタイル、趣味など)を詳細にイメージすることによって、出店エリア・業態・商品の価格帯なども変わってくることもあります。
例えば、どのようなイメージのエリアへの出店を目指していますか?
若者の街、エンターテインメント性が求められる流行の発信地 渋谷
おしゃれなショップやカフェが立ち並ぶトレンドの発信地 青山
外国人観光客の増加も目立ち、常に新しいことに挑戦し続ける活気あふれる街 原宿
高級ブランド店や老舗百貨店が立ち並び、日本屈指の繁華街として知られる銀座
洗練された都会の雰囲気が漂う東京屈指のビジネス街 大手町
選定するエリアによって、「ターゲットとするお客様は180度変わってくると言っても過言ではありません。
店舗コンセプトにあった立地を見極めることが大切です。
立地は「商圏(面)」「動線(線)」「地点(点)」の3つから場所を見極めることが基本です。
●商圏(エリア)
商圏の範囲(半径◯km、徒歩・自動車で◯分以内)、商圏人口(店舗に集客できる商圏範囲の人口)、来店する顧客が居住・勤務している地域の特性
●動線
店舗までの動線や方向(出店候補地への近づきやすさ、駅や施設などから店舗までの経路)、接近性(駅や施設などからの近さ、利便性)、競合店との位置関係
●地点
候補地や近隣の特性、店頭通行量(店の前をどのような人がどれ位通るのか)、視認性(店舗がはっきり認識できるか)、店舗の構造(出入口や柱、店舗設備などの位置や造り)
SNSやWEBによる集客が主流となりつつありますが、まずはお客様の目にお店を見えるようにして立ち寄ってもらうことが大切です。
お店は見えなければ存在しないのと同じですので、見えて初めてお客様に認知してもらえます。
しかし路面店や角地など見やすい場所にあるお店の家賃は高いので、主要駅から少し離れた駅だとしても視認性の良いお店を開業した方が結果的に良いケースもあります。
様々な角度から『この位置からお店がどう見えるのか?』を自分で歩いてみてみるのも1つの手です。
トレンドの移り変わりが激しい時代に、現状維持では生き残っていくことはできません。
競合が多い業界だからこそ、常に新しい手を打ち続けるために、マーケットの把握は継続的に行う必要があります。
消費ニーズ動向調査は、消費者のニーズや購買行動を把握するために実施される調査です。企業は、調査結果をマーケティング戦略や商品開発に活かすことで、顧客満足度の向上や売上拡大を目指すことができます。
1.消費者のニーズを把握する
消費者がどのような商品やサービスを求めているのかを把握することで、顧客ニーズに合致した商品やサービスを開発することができます。
2.購買行動を分析する
消費者がどのように商品やサービスを購入しているのかを分析することで、効果的なマーケティング戦略を立案することができます。
3.市場動向を把握する
市場全体の動向を把握することで、ビジネスチャンスを捉えることができます。
4.競合分析を行う
競合他社の商品やサービス、マーケティング戦略を分析することで、自社の強みや弱みを把握することができます。
他にもマーケティングには様々な手法があります。
独自に調査をする部分もあれば、外部に依頼することもある部分もあるでしょう。
調査結果の良いところ、悪いところ、強い点、弱い点をそれぞれ整理してまとめると、それらが競合の激化や商圏の縮小など、主に外的要因なのか、 それとも業種業態揃えや魅力づくりなど、主に内的要因なのかに分類します。
どの部分が一番あてはまる要素が多いかによって、活性化に向けた対策の方向性を探ります。
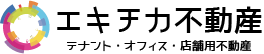
 お気に入り
お気に入り